セルフ・アドボカシー・スキルの考察①/文献調べ25-37
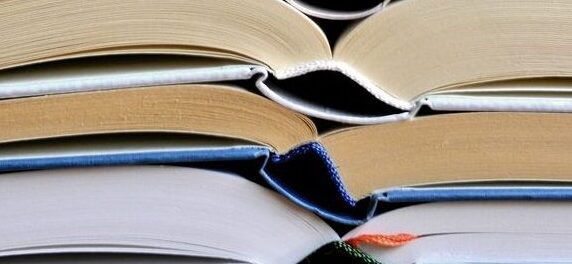
障害の開示について前回の記事で考えました。開示する際の不安や負担の一方で、職場への順応や定着をみると、開示の必要性が垣間見れます。
ただ、開示したから周囲が適切な支援を提供してくれるかといったらそうではありません。
障害特性はその人によって違うので、必要とする支援も異なりますから、障害のある人は「必要とする支援を伝える」というスキルも求められます。(ここでは、周囲の人たちの理解は前提として”あるもの”と仮定します)
今回は、『事例で学ぶ発達障害者のセルフアドボカシー 「合理的配慮」の時代をたくましく生きるための理論と実践』(金子書房,2017 著:片岡美華・小島道生)を抜書きさせてもらいつつ、セルフ・アドボカシー・スキルについて考えてみましょう。
(引用もしくは・が抜書き箇所)
セルフ・アドボカシーとは
アドボカシーとは「権利擁護」という意味ですが、直訳すると「自己権利擁護」ということになります。
その上でこちらの本では、
「自分の権利を自分で護ること」「法的な手段を行使して自らの権利を護ることだけでなく、例えば身辺に関わる決定を自分で行うこと等、日常的な自己主張の権利」(立岩・寺本、1998)
として、セルフ・アドボカシーについての定義を紹介しています。そして「自己決定」を大切なキーワードとして挙げています。
・自己決定は、現在、インクルーシブな社会において障害のある人が付帯となるには、とても重要な考え方
・「障害者の権利擁護(アドボカシー)とは、その当事者の生き方における自己選択と自己決定(self-decision)を中核とする社会的生活の自立を保障するために、個人や仲間が必要な支援を行う活動」(曽和、2008)
自己決定するということは、何かしらの選択肢が用意されているということですが、その選択肢は、多くの場合は支援者との間で考え出すものとなります。
ということは、自身の状態・状況を正しく自己理解した上で、わかりやすく他者に伝えるスキルが必要となります。
セルフ・アドボカシー・スキル
そこで重要になるのがセルフ・アドボカシー・スキル(自己権利擁護力)ということのようです。
著書の中でも、
自分の状態を自分で説明できる力(他者への理解を促す力)と自分が必要とする支援を他者に求められる力のおおよそ2つの力(Brinckerhoff,McGuire,and Shaw,2002)
と述べられています。
説明する力と、求める力ということですが、確かに微妙に異なるスキルのように感じます。特に、支援を求めるというのは、謙虚さを美徳とする日本文化においてはなかなかに難しいもののような気がします。
こういったことに注目した上で、セルフ・アドボカシー・スキルについて整理すると
「自分1人の力でできることと、周りの支援を得てできることがわかる力」すなわち現在の自分の状態や障害特性が理解できること。「何を、どのようにして欲しいのかを他者に求める力」(具体的にこういう支援をお願いしたいと相手に提唱していく力)片岡(2010,2014a)
と定義できるのだそうです。
ーーー今回の抜書きはここまでーーー
所感
自己理解と提唱する力がセルフ・アドボカシー・スキルということのようですが、その前には「障害受容」というこれまた大きな課題があるのでしょう。
こちらの本では、セルフ・アドボカシー・スキルが合理的配慮を受けるための意思表明として捉えられているのですが、提供する側(会社)も本人がさまざまな課題をクリアしながら申し出ているということを理解する必要があると思います。
また一方で、申し出た支援が提供されないという事態も往々にしてあると思います。そんな時、「会社は何もわかってくれない」と思ってしまいがちかもしれませんが、セルフ・アドボカシー・スキルの定義する「現在の自分の状態や障害特性を理解」し、「何を、どのようにして欲しいのかを他者に求める力」が自分にどの程度身についているのか、身についていないとしたらどうやって身につければいいのか、という視点で考え直すことも必要だと思いました。
では、また次回!
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 前回に引き続き、『事例で学ぶ発達障害者のセルフアドボカシー 「合理的配慮」の時代をたくましく生きるための理論と実践』(金子書房,2017 著:片岡美華・小島道生)を抜書きさせてもらいつつ、セルフ・アドボカシー・スキルについて考えてみます。(引用もしくは「・」の箇所が抜書き) […]