D&Iが組織体に与える影響②/文献調べ25-40
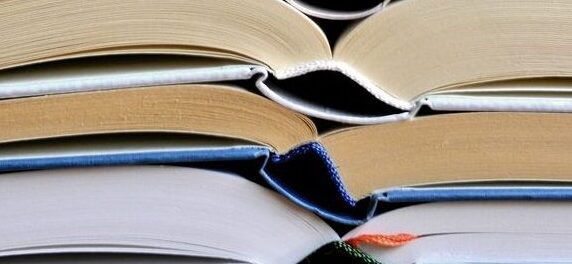
前回の続き、内部監査人協会(IIA)の論文から、ダイバーシティが組織体に与える影響について見ていきます。(・は論文からの抜書き箇所)
グローバル化した環境への適応
・多国籍組織体は事業活動圏内の各文化をしっかり理解し、誰も疎外することなく、ダイバーシティの議論にあらゆる面を考慮したインクルーシブな環境を助長するように努めなければならない
・「グローバル化の力が実際に奨励しているのは、1つの退屈な地球村を作ることではなく、文化の多様性を広めることである」(ソニーピクジャーズエンターテイメント社CEOマイケル・リントン氏)
ダイバーシティとインクルージョンの方針を導入する際の課題
・進め方を誤ると、ダイバーシティとインクルージョンの施策は単に効果がないだけでなく、組織体が改善に努めているまさにその分野に、最終的に逆効果となる可能性がある
・無意識の偏見をなくす研修が広く実施されているにもかかわらず、その有効性に関する証拠は全く様々
・調査結果は、ダイバーシティとインクルージョンを推進することは強制すべきではなく、従業員の考えや意見を管理する要素として利用すべきでもないことを示唆している。
・十数年に及ぶ社会科学の研究で明らかになったのは、ごく単純な心理だ。すなわち、規則を課して再教育を施すという方法でマネージャーを責めたり、その面目を潰したりしても、彼らを本気で取り組ませることはできない
・内部監査を活用している組織体は、インクルーシブとみなされる行動を従業員に起こさせる状況を作ることを優先することができる
・組織体がダイバーシティとインクルージョン憲章を検証する際に参考にできるリソースの1つは「グローバル・ダイバーシティ・アンド・インクルージョン・フレームワーク」
▷伝達_好影響について組織体内外に伝達する
▷追跡_目標を設定して、進捗状況をモニターする
▷研修_学習ツールを提供
所感
内部監査としての役割を果たす中で、D&Iをどう捉え、どう推進するかという視点について書かれていましたが、その多くは、DEI推進担当者にとっても参考になるものなのでは、と思います。
特に強制的な学びが、反発を生み出すというのは、この頃よく聞く「バックラッシュ」そのものではないでしょうか。ただし、推進する上では確かに「教育」「研修」が有効なツールであることも間違い無いと思います。
どういう目的で、どういう手段で届けるか。正しく、慎重に設計することが肝要だと感じました。
コメント