障害者雇用におけるイノベーションを考える②/文献調べ25-45
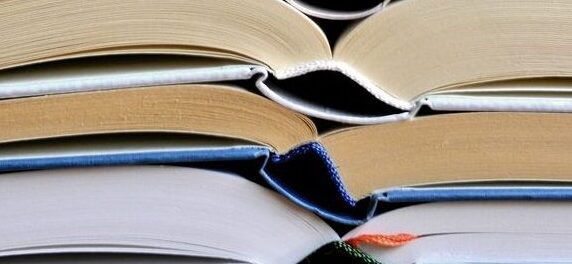
前回に続いて、「障害から始まるイノベーション」田中真理・横田晋務(2023,北王路書房)を抜書きしながら、障害者雇用におけるイノベーションを模索していきます。本著は2章において、障害別の特性や社会的バリアについて述べられていますが、今回は「発達障害」の節を抜き書きさせてもらいながら、考察します。
(・が抜き出し部分。それ以外は私の所感)
○発達障害から見た社会的バリア
日常生活上のバリア
・周囲の人から障害が見えづらい、理解されづらいという特徴。障害であるという可視性が低い。
・外見上の特性と行動特性のギャップによって発達障害のある人は、社会的排斥を経験しがち
・社会的排斥は、学校場面であれば、いじめという形で表れ、心理的バリアである周囲の人たちの否定的な態度によって引き起こされる
・社会的排泄は、職場やプライベートでも生じると考えられる
・社会的バリアとして排斥を考える場合、ASD児・者のおける機能障害と、心理的バリアという両面を考慮することが必要
修学・就労上のバリア
・情報的バリアや制度的バリアが挙げられる
・情報的バリアは、情報提示のされ方によって、同等の情報を得ることができないバリア
・修学では、極端にいえば、勉強さえできれば大きな問題は生じないかもしれない
・社会人として働くにあたっては、人間関係の構築や対人コミュニケーション上で求められることが格段にj複雑化
・社会人になって問題が顕在化することもあり、発達障害と新たに診断された対象のうち、約5割が成人等データもある
・大人の発達障害で特に問題になるのは、ASDとADHD
・就労上の社会的バリアとしては、求められることと発達障害のある人のできること・得意なこと等とのミスマッチといった制度的なバリアが挙げられる
・また、口頭のみでの曖昧な指示や、臨機応変に対応する度合いが大きな指示等の情報のバリアも考えられる
・さらに、このような障害特性への理解や支援がないことで、仕事上でのミスが誘発。ミスを繰り返すことにより、心理的バリアとして周囲の目や態度が否定的になり、結果として職場の適応に悪影響も与えることも考えら得る
所感
発達障害の「低い可視性」による周囲への分かりにくさ自体が、就労上の大きなバリアとなります。
なるべくコミュニケーションを簡便化・効率化して仕事を進めるチームが良しとされる風潮もありますし、実際に好業績チームには「暗黙の協調」が存在するという研究結果もあります。
これらがいい職場の定義の構成要素と捉えられているとも考えられますが、テレワークや働き方改革によって職場での関わりが希薄になっている現代において、発達障害の方の「わかりやすさ」に着目することは、職場のつながり創出や生産性向上のきっかけになると考えます。
コメント