セルフ・アドボカシー・スキルの考察②/文献調べ25-38
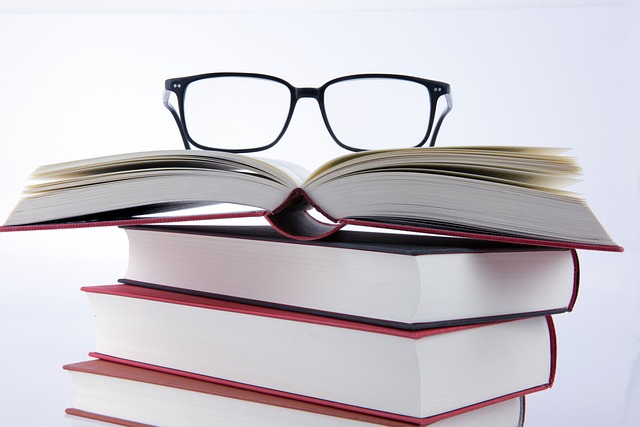
前回に引き続き、『事例で学ぶ発達障害者のセルフアドボカシー 「合理的配慮」の時代をたくましく生きるための理論と実践』(金子書房,2017 著:片岡美華・小島道生)を抜書きさせてもらいつつ、セルフ・アドボカシー・スキルについて考えてみます。
(引用もしくは「・」の箇所が抜書き)
セルフアドボカシーを支える自己理解
セルフアドボカシーは「自己理解」が支えていると書かれています。自己理解は、支援の必要性や欲しい支援内容を訴えるために重要となるからのようです。
・新しい環境、とりわけ「自主性」や「応用性」が求められる職場にあると、さまざまな力量がついてきていたとしても、これまでと同じようには課題を遂行できない場合がある
・自身のニーズに基づいて欲しい支援の具体的な内容について自分でわかっていないと、当然、自分に合った支援をえることができない
とあります。
そして
・発達障害のある子どもの自己理解を向上させるには、成功体験などプラスの経験に対して他者から評価されることの有効性を報告(小島,2011)
とも書かれています。
職場においても1on1などを用いて仕事への取り組みや、経験に対するポジティブなフィードバックをすることで、自己理解が深められるのではないでしょうか。
自己理解教育
セルフアドボカシーを支える自己理解教育のまとめとして、以下が挙げられています。
- 自分のポジティブな面について知る活動を取り入れる。
- 障害を理解するための学びを取り入れる。
- 得られる支援について知る。
- 具体的行動につなげる。
ポジティブな場で自己理解を深める。さらには、自身の障害についても学ぶ(例えば、認知の歪みがあるなどは、教育しないと自分でも理解しづらいものかもしれません)。
そして、支援について知り、具体的行動(支援を求める)にうつるというステップです。
具体的行動の際には、”提唱力_当事者自身が環境を変えるために必要な支援を相手に伝えていく力”も必要と書かれています。
・セルフアドボカシーにおいては、相手にただ伝えるだけでなく、わかりやすく具体的に伝え、交渉し、支援を獲得していくだけの言語力、とりわけ社会性を伴うコミュニケーションが求められる
これもとても大切なスキルですね。「周囲が理解してくれない」と考える前に、わかるように伝えられているかという自責思考が必要なのかもしれません。
所感
セルフアドボカシーについて考えました。雇用の場を考えた時に、合理的配慮の提供が会社側の責任だとしたら、自己理解し、支援について知り、適切に分かりやすく支援を求めるスキルを身につけることが、障害のある人の責任だと思います。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
コメント