「障害者雇用は法律で決められてます」で、人が動かないワケ/文献調べ25−27
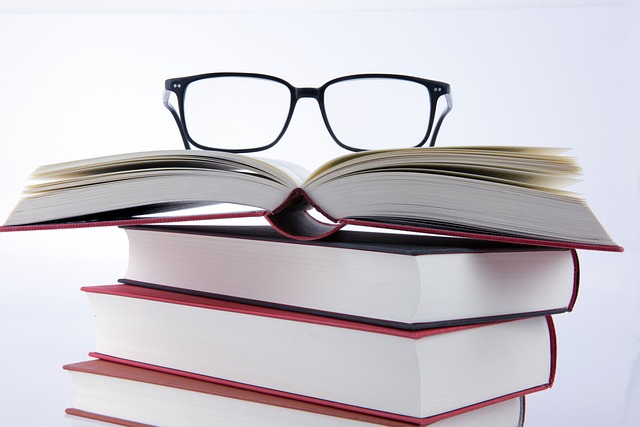
「合理的配慮は、気遣いとか気配りではなく、法的義務です」
そういった言葉を伝え続けても、なかなか社内の理解が進まない。よく伺うお話です。
法律やルールを伝えても、なぜ人は動かないのか。
今回はハーバードビジネスレビューの記事(差別の心理学:ダイバーシティ施策を成功させる方法 (Harvard Business Review, July-August 2016))から、ダイバーシティ施策の失敗例を元に考えてみます。
人はなぜ動かない
記事によると、「必須のダイバーシティ研修」や「苦情申立て制度の設置」「罰則」といった”強制的手法”によってマネジャーの考え方や行動を取り締まって訴訟を未然に防ぐように図ってきたものは、皮肉なことに偏見を強化してしまったようです。
その原因について
社会科学者によると、人間はみずからの自律性を主張するために規則に反発することが多い。
と述べられています。
マネジャーに抜擢される人たちというのは、仕事の能力ももちろんですが、「自律性」も会社から評価されていると思われます。その「自律性」の高さが、ダイバーシティに関する強制的なルールの押し付けによって反発を生むということでしょう。
以下抜書きです。
・ダイバーシティに取り組む際、企業幹部は古典的な指令・制御手法を好む。
・しかしながらこの手法は、人間が変わるための動機づけに関する、筆者らが知りうる知識のほぼ全てに反している。
・規則を課して再教育を施すという方法でマネジャーを責めたり、その面目を潰したりしても、彼らを本気で取り組ませることはできない
障害者雇用に置き換えると・・
これは障害者雇用においても同じようなことが言えるかもしれません
例えば、
「合理的配慮は法律で義務なのでやってください」
「障害者雇用は法律で決められています。受け入れについて理解してください」
こういった発信は大切ですし必要であることに異論はありませんが、こういった言葉だけではなかなか人が動かないというのは、担当者の方々の悩みの一つかもしれません。
人を動かす3つのアプローチ(HBRより)
解決策として、記事には”良好な成果を上げている企業は3つの基本原理を適用している。具体的には、マネジャーにダイバーシティ問題の解決に当たらせる、マネジャーと異なる集団に属する人々が接するようにする、変化のために社会的責任を奨励するというもの”と示されています。一言で言うと「関与」「交流」「社会的説明責任」の3つです。
これを障害者雇用に当てはめて考えてみます。
関与:解決の当事者になってもらう
「特定の見解を支持するようなやり方で行動するように人々を促すと、彼らの意見はその見解のほうに近づく(認知的不協和の解消)」という人間の特性を用いる。
⇒ 例:障害者と一緒に職場改善プロジェクトに取り組む
交流:集団間の壁をなくす
「肩を並べて働くことで固定観念は打ち砕かれ、より平等な登用や昇進へとつながる」という実践知を活用。
⇒ 例:普段接点のない部門の人と仕事をする機会をつくる
社会的説明責任:周囲の目を意識してもらう
周囲によく見られたいという人間の欲求を刺激する。
⇒ 例:障害者雇用サポーターを事業所(部門)ごとに置く
また、HBRでは「メンタリング」や「クロストレーニング」のように、“ダイバーシティのためにやってます”と打ち出さない施策のほうが効果的だと指摘しています。
障害者雇用においても、「障害者のため」という冠を外し、「職場全体のため」「みんなが働きやすくなるため」という文脈で設計すると、受け入れやすくなるのではないでしょうか。
まとめ
人は法律やルールで強制的に変わっていくのではなく、人と人とのまっすぐな関わりの中で変わっていくんだなと再確認しているところです。
組織文化の醸成や受け入れ意識の向上といった目標を掲げら、障害者雇用推進に取り組まれている会社さんがありますが、まさにそうした視点が、職場の多様性を根づかせる第一歩になると考えています。
※「人の心に寄り添った障害者雇用支援」についてご興味ある方はお気軽にご相談ください
コメント