障害者雇用とダイバーシティ・マネジメント/文献調べ25−12

障害者雇用とダイバーシティ・マネジメントについては、
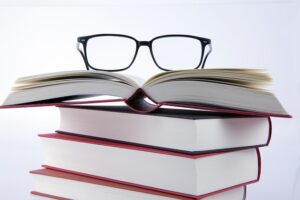
をかつて取り上げましたが、今回は「障害者雇用とダイバーシティ・マネジメント-特例子会社スミセイハーモニーを事例として- (牛尾・志村、2018)」を参考に、特例子会社の事例をもとに考察してみます。
以下、重要と思う部分を抜書きしつつ考えてみました。
企業側の課題
本論文では
法定雇用率達成企業は未達成企業と比較して企業パフォーマンスが低いことを検証している(長江、2014)
を取り上げています。理解としては「納付金や助成金の学が少ないこと」「合理的配慮などの措置」の2点としています。
障害者側の課題
・身体障害者よりも精神障害者の方が、配慮を多く求める傾向
・身体障害者では「仕事内容」や「給与」を重視する傾向。精神障害者では「障がいへの配慮」を重視する傾向
・障害者雇用においては、障害者個々人に対するきめ細やかな対応が必要となる。企業、特に人事部が柔軟な作業環境を作ることで、障害者個々人のニーズに的確に応える必要性を示している(Baumgartner et al., 2015)
障害のあるないに関わらず、会社側へのニーズはどの従業員でも抱えるものでしょうが、機能障害であれ、社会モデルでの障害であれ、合理的な配慮を必要とする点は障害者特有のニーズといえます。
また本論文では、「障害者の主体性」についても言及している点は共感する部分です。
配慮だけを求めるのではなく、配慮によって能力を発揮し、会社に貢献するという主体性が求められます。
ダイバーシティ・マネジメント
「障害者自身にとっては働きやすさや働きがいを、企業にとっては経営成果を追求する段階」であるとしながら
・障害のある者とない者との間でのコミュニケーション、相互理解、相互作用が不可欠
・障害者雇用に取り組み、経営面でも成功している企業を見ると、利潤を追求しつつも、ダイバーシティ・マネジメントによって障害のある社員の潜在能力を最大限に活かす職場環境作りに尽力している
・決して競争優位のために障害者の雇用に取り組むという順序(発想)ではない
・障害者雇用は近視眼的に見れば、コストがかかる。しかしその負担を引き受け、障害のある社員の潜在能力を最大限に活かす職場環境作りに尽力することで、長期的かつ全体的には、競争優位を確立し、利潤をもたらしうる(Thomas、2010)
と示しています。
コミュニケーションにしても、コストはかかります。これまで普通と思っていたコミュニケーションスタイルを見直すことになるかもしれないからです。しかし、その負担を乗り越えた先にベネフィットがありえると述べられています。
合理的配慮と比較優位
眞保(2014)は「合理的配慮は比較優位の視点から行うべきだ」としています。比較優位とは、D・リカードが比較生産費説で主張した概念で、これを参照すると、障害者個々人の得意なものを見いだし、それを活かしていくというのが、比較優位の考え方となります。
・比較優位の考え方にしたがって、障害者個々人を戦力化し、質の高い雇用を実現していたり、また、障害者個々人の得意なことに注目して分業体制を構築することで、成果を上げている企業が、複数あった(眞保,2014a)
・眞保の調査分析によれば、障害者の戦力化には、業務に精通している指導者によるOJTが重要となる
先ほどの障害者のニーズに合致するものですが、OJTは「配慮」という視点のみならず、働きがいの向上にもなるもので、定着支援の一環でもあります。
普遍化
・有村は、個別的対応の中にも共通点を見出していくという「普遍化」の発想が、今後ますます重要になると述べている(有村、2014)
・普遍化の契機を見出し、それを、企業全体における働き方、制度、組織文化等の変革へと拡げていくことができれば、経営成果を生むことになる
合理的配慮は、障害者への優遇といった間違った認識につながることがあります。認識を改める必要性は当然にありますが、同時に、配慮自体が会社全体への変革につながるものであれば、配慮を提供された人のみならず、変革の恩恵を享受できることができ、それが成果につながるようです。
最後にスミセイハーモニーさんでの事例を、D・キムの組織の成功循環モデルに当てはめて考察しています。
関係の質・・・手話や表彰によるコミュニケーションの促進や褒める文化の浸透
思考の質・・・グループ長を障害者が務めるなど、仕事に対する向上心
行動の質・・・リーダーとして、メンバーがそれぞれの仕事を遂行できるよう、指導、フォロー
結果の質・・・ミス発生件数が極めて少ない、など
所感
障害者支援においては、支援者的な立場になればなるほど、会社としての成果という視点が置き去りになりがちです。一方で、会社としての成果を求めすぎると、障がい者への配慮は置き去りになります。
本論文では、企業の課題、障害者の課題の両面から考察し、ダイバーシティマネジメントの目的に立ち返った上で、合理的配慮を比較優位の視点で考えるという、障害者雇用を一段高いところから見渡していました。
障害者雇用推進においては、経営トップ、現場のトップの理解とコミットメントが不可欠です。「合理的配慮は法律で決められているから必要なんです」という説明では、真の「障害理解」は得にくいです。
組織の成功循環モデルなども用いられていますが、「だから障害者雇用は自社に必要なんだ」という論理の構築と実践と検証のサイクルが今後ますます必要だなと思いました。
コメント