職場での「障害の開示」について考える/文献調べ25-36
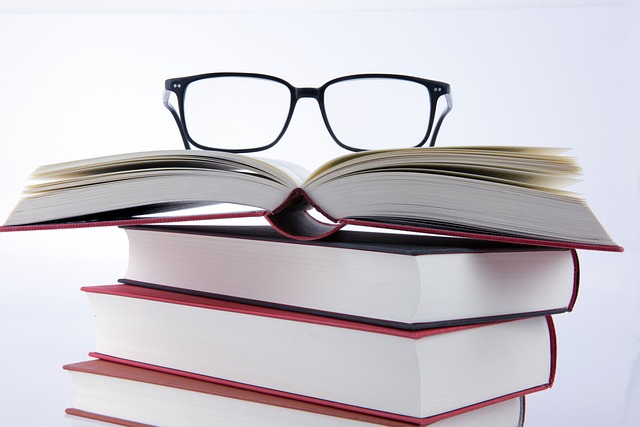
職場で障害を開示するか否かは、障害のある人にとっては大きな意思決定だと思います。
開示することで支援制度を利用しやすくなる一方で、スティグマの影響を受けるかもしれないという不安も高まるでしょう。
今回は、「障害という経験を理解する 社会と個人へのアプローチ」(ダナ・S・ダン編著,北大路書房,2025)の「第13章 職場における障害」を抜書きしながら、(海外の事例ではありますが)障害の開示について考えます
障害の定義
本章では冒頭で”障害が職場でどのように作用するかを議論する前に、「障害」を定義することが重要。その試みには議論の余地があることを認識する必要がある”としています。
個人モデルと社会モデルの概要について記載した上で”一つ又は複数の主要な生活活動を実質的に制約する身体的または精神的な機能障害」と定義(ADA,1990)”とあるので、個人モデルの定義を用いているのかなと思います。(私の読み解きが不十分なのかもしれませんが・・)
障害の開示
開示については
職場で自分の障害を開示するという決断が、特に組織が個人に合理的配慮を図ることを保証する唯一の方法であるという点で、重要な意味をもつことを示しているかもしれない(Working Mother Research Institute,2016)
と記されています。特に、精神・発達や内部障害のような、他者から見えない障害については「開示」の有無は配慮の提供には大きく影響するのは、想像に難くないです。
参考までに、「障害者の就業状況等に関する調査研究(障害者職業総合センター 2017年4月)」においても、
障害の開示を前提とする支援制度の利用によって、職場定着が促進されることが考察される
と記されています。

開示のリスク
前述の通り、障害を開示することは大変勇気のいることだと思います。
その理由は、残念ながら職場に限らず社会において、障害に対する偏見や差別が根強くあるからだと思います。
職場における差別については
非言語的な行動(例:目を合わせない、にやける)、言語的な行動(例:否定的な言葉)、パラ言語的な行動(例:声の調子)など、より微妙な形の差別が起こることもある。このような微妙な形の差別は些細なことに思えるかもしれないが、研究によると、仕事の満足度の低下・離職意向の増加・仕事のパフォーマンスの低下など、あからさまな差別的行動よりも否定的な結果をしばしばもたらすことが示されている(Lim,Cortina,& Magley,2008)
とあります。差別が仕事の満足度の低下・離職意向の増加・仕事のパフォーマンスの低下につながるのはうなづけますが、それが”あからさまな差別的行動よりも否定的な結果”をもたらすのは驚きです。
こういったリスクを考えると、開示に前向きになれない方がいても仕方ないよなーと思ってしまいます。
加えてこうあります。
障害者は、自分のスティグマ化されたアイデンティティを「受け入れる」(スティグマ化されたレッテルを公にも私的にも受け入れる)か、「見過ごす」(レッテルを私的に受け入れるが他者には隠す)か、を決めなければならない (Ashworth&Humphrey,1998)
障害の開示が本人に大きな負荷を負わせてしまう現実を、非障がい者はもっと知る必要があるなと思いました。
開示のメリット
一方で、開示による効果も示されています。
障害を開示した障害者は、仕事のパフォーマンスを向上させ、仕事に関連したストレスを軽減するための配慮を受けやすくなるかもしれない
障害を開示することで、「表に出ている」ことに安心感を覚え、隠れたアイデンティティを秘密にし通すことを気にしなくてすむかもしれない(Bowen & Blackmon,2003)
障害を開示すれば職場で障害の影響を受けている人が大勢いることが示され、同じような経験をしているかもしれない同僚に「自分だけではない」と伝わる可能性がある(Nittrouer,Trump,O’Brien,&Hebl,2014)
パフォーマンス向上の根拠は、開示したことに安心感によるものかなと思います。
そして開示により、同僚にも恩恵がある可能性があることは、職場全体で見て大きなメリットなのではないでしょうか。
考察
国内の調査においても、開示と定着の相関が示されています。合理的配慮の提供は開示が前提になっているので、より重要な意思決定であることが伺えますが、そこには本人の負担感や不安感も伴うことは、よくよく理解していく必要があります。
同業の方で「障害理解を促すことは、組織文化の変容そのもの」とおっしゃられた方がいますが、言い得て妙だなと改めて思いました。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 障害の開示について前回の記事で考えました。開示する際の不安や負担の一方で、職場への順応や定着をみると、開示の必要性が垣間見れます。 […]