ダイバーシティとインクルージョンの差異/文献調べ25-42
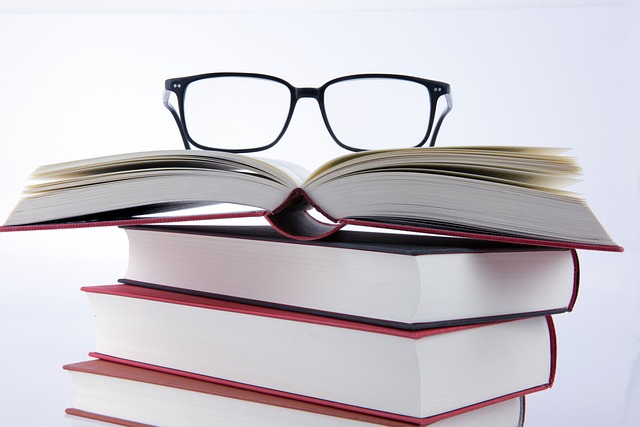
現在、受講しているILCの講義の中で、「インクルージョン」のフレームワークについて学びました。
これまでDE&Iの概念や差異については本ブログにて考察してきましたが、改めて『ダイバーティとインクルージョンの概念的差異の考察』(脇夕希子,2019)「ダイバーシティとインクルージョンの概念的差異の考察」『商経論叢』60(2), pp.33-44.)を抜書きさせてもらいながら、企業におけるインクルージョンを整理します。(・箇所は抜書き)
目的
こちらの論文では、大きく2つ目的が示されています。
- ダイバーシティ、インクルージョンの間の概念的差異を明らかにすること
- 日本の企業のダイバーシティ・マネジメントの取組で使用されている用語がその概念に沿った取組であるかを検討すること
特に1つ目の概念的差異について、「インクルージョン」に注目して見ていきます。
インクルージョンの概念
インクルージョンについては、社会・教育・企業といった領域で議論されています。
・EU諸国では、社会的排除の対語として社会的包摂が政策上の用語となった
・教育分野では、教育にアクセスできない特別なニーズ教育が必要な子供達を地域の学校の学級の中で教育するあり方をインクルージョン教育と考える
・ダイバーシティマネジメントの起点である北米では、ビジネスの中でダイバーシティとインクルージョンを区別し、インクルージョンをグループの中で十分貢献することができると定義
・ある特別な事情を抱えたメンバーがそれぞれの組織体の中に包含されている状態を想定
・個々人が参加を許可された、貢献することができたという程度(Miller,1998)
・従業員がワークシステムの中で他者から「中の人」として受け入れられている、扱われている程度(Pelled et al., 1999)
・コミュニケーションや意思決定プロセスに従業員の十分な参加が歓迎されたという従業員の認知、および組織に対して従業員の独特な貢献が評価されたという従業員の認知(Mor Barak,2017)
・インクルージョンは、組織の中に入るだけでなく、その中で自身が受け入れられている、貢献できている、その貢献が評価されている、と従業員自身の認知が必要
これらから、筆者の脇先生はインクルージョンについてをこのように捉えています。
・インクルージョンは従業員の認知によるものである。その認知は次の3つの側面
・第1は独自性への価値づけ。すなわち、自身の独自性が価値づけられ、評価されていると従業員が認知すること
・第2は所属の観点。すなわち、従業員が組織の中に所属していると認知すること。認知させるには、意思決定プロセスへアクセスできる、公式・非公式情報にアクセスできる、グループや組織全体への参画への働きかけ、が求められる
・第3は 自分は公平に扱われているという認知。企業が従業員をインクルージョンさせるためには、これらを従業員に認知させるマネジメントが求められる
先生もおっしゃられているように、「認知させるマネジメント」が求められており、なおかつ、一番難しいプロセスだと思います。
独自性の価値を自信が認知していない場合もあったり、公平感についても、例えば業務やPJの特性によるアサインメンバーの違いが不公平と捉えられる場合もあったりと、認知させるマネジメントが一筋縄ではいかないことは想像に難くないです。
ダイバーシティの概念
インクルージョンとの比較に向けて、ダイバーシティの概念も整理されています。
・グループの構成(Miller,1998)
・組織で異なる人々を雇用することで達成(Neharika&Chari,2015)
・観察できる特性(性別、人種、年齢)と観察できない特性(文化、認知、教育)の両方を含むメンバー間での人口動態上の違い(Mor Barak,2017)
これらを踏まえると、ダイバーシティは人口動態上で異なる人びとを組織の中で雇用することを意図
表層的・深層的ダイバーシティといった違いもありますが、インクルージョンが「活用のphase」とすると、ダイバーシティは「状態のphase」ともいえるでしょうか。状態にもっていくのも大変だと思いますし、特に深層的なダイバーシティは活用段階で徐々に明らかになるものでしょうから、状態のグラデーションもあるはずです。しかしながら概念を見渡す限り、個性の活用であったり所属感であったりという認知を含むものではないのかなという理解です。
ダイバーシティ・マネジメントと日本企業の取組
脇先生は、企業におけるダイバーシティ・マネジメントについて別の論文で
個々人の多様なバックグラウンドを受容し、組織内に参画させることを前提とする。その上で、その多様性が企業にとって、戦略的成果をもたらすように、個々人の能力を最大限活用できる組織改革を自発的にかつ長期的におこなうこと(脇,2009)
と定義され、キーワードとして
- 組織内参画
- 組織内公正
- 組織の戦略性
- 組織変革
の4つを列挙されています。この4つをダイバーシティとインクルージョンで整理すると
- 組織内参画は、人口動態上の多様な人材という意味ではダイバーシティ、雇用した後活用していくという点ではインクルージョンの観点を意図
- 組織内構成は、インクルージョンの観点
- 組織の戦略性は、ダイバーシティ、インクルージョンを実施する際に欠かせない視点。ベネフィットの観点がないと、継続・定着しない可能性がある
- それらを包含する組織へと自発的に変革していく組織変革
であると示されています。
個人的には特に戦略性の部分が大事だと考えます。障害者雇用もまさにそうで、ベネフィットの観点(法令遵守といった守りの戦略性の対となる、攻めの戦略性の必要性)を示すことが、あらゆる階層での受け入れ意識や推進意欲の高まりには肝要だと感じます。
また、本論文では企業による取り組みを2つ紹介された上で
今後企業はダイバーシティ・マネジメントの取組の一環として、ワーク・ライフ・バランス施策に着手する際は、3つの観点(独自性の価値付け、所属感、公正感)を含んだ、企業の施策や人事制度の変革が求められる
との課題意識を示されています。
所感
概念的な差異としては、状態or活用といったものが指摘されるのかなという理解です。一方で、マネジメントとして整理すると、DとIの概念が散りばめられているものだと感じます。アファーマティブアクションなのかダイバーシティ・マネジメントなのかという、もしくはどちらも含むものなのか。その先に企業がどういった成果を期待するのかを考える上で、先生が指摘されていた課題感は心の焼き付ける必要があるなと感じました。
コメント